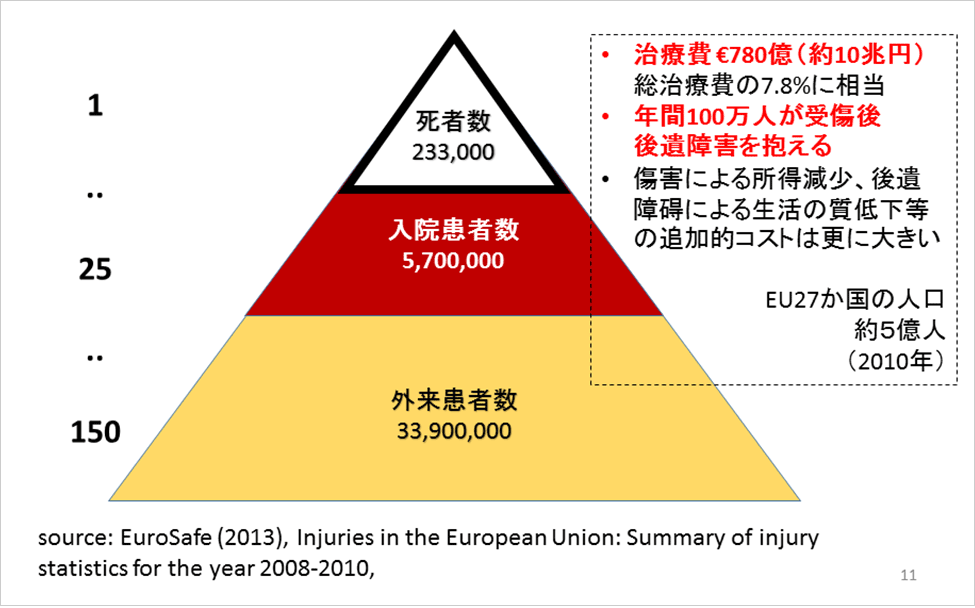日本の傷害ピラミッド
1. 日本人はどのくらいケガをしているか?
一体,日本人は一年間にどのくらいケガをしているのだろうか?また,その原因やひどさの程度はどのような内訳になっているのだろう.単純な問いだが,答えるのは難しい.
この問いに答えてくれるのが厚生労働省の「患者調査」である.「病院及び診療所を利用する患者について,その傷病状況等の実態を明らかにし,医療行政の基礎資料を得ること」を目的として,3年に一回の頻度で実施されている調査である.本稿執筆時点(平成28年3月)で最も新しいのは平成23年度調査であり,過去,平成20年度,平成17年度,平成14年度,平成11年度などに実施されている.
全国には1万3000余箇所の病院と〓箇所の診療所があるが,このうちの約〓%が調査対象となっている.平成23年度調査の場合,病院についてはほぼ全数に近い6,428病院が,診療所については全数の〓割に相当する〓5,738診療所(歯科を除く数字)が調査対象である.いずれも10月のある日を選んで,その日に入院している患者数,外来で来院した患者数が,その診療内容とともに記録され,報告される.
傷病の状況については,「疾病,傷害および死因統計分類」(ICD)と呼ばれるWHOの定める分類体系に従って調査されており,ケガに相当するのは分類XIXの「損傷,中毒及びその他の外因の影響」という分類項目である.これには交通事故によるケガも,工場での労働災害によるケガも,家庭や学校でのケガも,すべてが含まれている.
平成23年度の患者調査によれば,病院及び診療所の推定入院患者数は12万4800人,推定外来患者数は31万7600人であった.どちらもある一日の調査結果である.患者調査は,更に「総患者数」を推計している.これは「調査日現在において継続的に医療を受けている者(調査日に医療施設で受療していない者を含む)の数を次式で推計したもの」である.
入院患者数+初診外来患者数+(再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7))
この推計式の意味,特に第三項の意味は少しわかりづらいが,以下のように意味づけることができる.外来患者は通常何度も医療施設を訪れるが,その平均診療間隔がひと月(30日)であったとしよう.すると,この調査日現在において継続的に医療を受けているものの中には,たまたま調査日に訪れた再来患者のほかに,別の日に医療施設を訪れる患者がいるはずであり,こうした再来患者の合計は,調査日における再来外来患者数に平均診療間隔(30日)を乗ずれば求められる.調整係数は再来患者が日曜日(あるいは他の休診日)に訪れることはないことを考慮して6/7を乗じたものである.
以上の調査結果をまとめると,傷病大分類が「損傷,中毒その他の外因」である調査日時点での患者数等は表1のようになる.
表1 損傷,中毒等による推定入院患者数,推定外来患者数,受診率,総患者数
| 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推定入院患者数(千人) | 1.5 | 6.1 | 22.6 | 94.2 | 124.8 |
| 推定外来患者数(千人) | 45.4 | 54.6 | 119.3 | 96.5 | 317.6 |
| 人口(千人) | 16,705 | 27,757 | 53,579 | 29,173 | 125,525 |
| 入院受診率(10万人対) | |||||
| 外来受診率(10万人対) |
出典:患者調査(平成23年度)
2. 年間新規傷害件数
上記の調査結果はいずれもある一日あたりの数値であることに注意してほしい.調査目的が「医療行政に資する」とあるように,病院の病床数規模は十分か,医師数と患者数の比率は適正か,といった問題意識からすれば,一日当たりの患者数が必要になることは理解できる.
しかし,日本人が年間何回ケガをしているのか,という問いに答えるにはこれでは不十分である.本書に登場する多くの傷害データは一年間あたりの発生件数であり,これと比較するためには,上記のデータをもとに,新たな傷害の年間発生件数を求める必要がある.このためには上記のデータを少し加工しなくてはならない.
入院患者数の方は,一年を通じてこの調査日と同数が入院していたとすると,継続的に治療を受けている患者数は,調査日の入院患者数に365をかけて,平均在院日数で割ればよい.幸い,調査日の前月に退院した入院患者についての平均在院日数が調査されているのでこれを平均在院日数として用いる.すると患者数は以下のようになる.
表2 年間新規入院患者数
| 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推定入院患者数(千人) | 1.5 | 6.1 | 22.6 | 94.2 | 124.8 |
| 平均在院日数(日) | 5.9 | 12.6 | 21.6 | 46.7 | 33.4 |
| 年間入院患者数(千人) | 92.8 | 176.7 | 381.9 | 736.3 | 1387.7 |
| 人口(千人) | 16,705 | 27,757 | 53,579 | 29,173 | 125,525 |
| 年間入院率 | 0.0056 | 0.0064 | 0.0071 | 0.0252 | 0.0111 |
入院患者の半数以上は65歳以上の高齢者であり,一方外来患者数の方は難しい.年間の延べ外来患者数は調査日の外来患者数に365日を乗じた値であるから,37万人/日×365日=13,505万人)となって日本の総人口を超えてしまう.これは同一の患者が何回も来院するからだ.では,平均すると何回くらい来院しているのか?この数字は公表された患者調査の集計結果からは得られない.しかし,患者調査では外来患者を新規外来と継続外来に分けて調査しており,これを用いれば平均外来回数は次式で求められるから,年間の外来患者数も推計することができる.
平均外来回数=(初診外来患者数+再来外来患者数)÷初診外来患者数
患者調査によれば,損傷,中毒等による患者数の場合で平均外来回数は約5回である.したがって,年間の外来患者総数は年齢階級別に次表のように推計される.
表3 年間の通院患者数
| 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推定外来患者数(千人) | 45.4 | 54.6 | 119.3 | 96.5 | 317.6 |
| 平均在院日数(日) | 5 | ||||
| 年間外来患者数(千人) | 23,185 |
つまり,日本では一年間に平均すると138万人がケガや中毒などの理由による傷害のために入院しており,また,2,319万人が通院しながら治療を受けていることになる.両方を合わせれば,2,457万人となり,確率は2,457万人/12553万人=0.19.日本人の5人に一人が一年間の間に入院または通院を要するケガや中毒をしていることになる.
これは生活実感からすると予想以上に大きい.おそらく,途中で通院先を変えたり,複数の医療施設に並行して通院していたりするためであろう.実際,欧州における傷害による死者数と通院患者数の比率は1:150であるが,これを日本について計算してみると1:700となっていまう.しかし,その実態を明らかにする材料はなく,数字をこれ以上つめていくことはできない.
仮にこの数値を前提とすれば,4人家族であれば,家族全員が一年間に一度もケガ等で病院のお世話にならない確率は誰かが入院または通院する確率は(1-0.19)4となり,約43%である.家族の誰か入院または通院する確率は一年あたり1-(1-0.19)4となり約57%である.
しかし,この確率は家族の年齢構成によっても大きく異なる.表2や表3に示すように,入院や通院の確率は高齢者ほど高い.したがって高齢者を含む世帯ほど入院,通院を要するケガをする確率は高くなる.
次表にいくつかの典型的な家族構成の場合のいくつかの確率を次の表に試算してみた.
表4 典型的な家族構成の場合の年間入院,通院者の発生する確率
| 家族構成 | 若者単独世帯 15歳~34歳 |
四人の核家族 夫婦64歳以下 子供14歳以下 |
夫婦と高齢者 夫婦64歳以下 同居65歳以上 |
高齢者のみの 夫婦世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 一年間に家族全員が入院も通院もしない | 計算中 | |||
| 一年間に誰かが通院を要する傷害を負う | ||||
| 一年間に誰かが入院を要する傷害を負う |
3. 傷害による死亡件数
一方,傷害,中毒等が原因で死亡する者は一体どのくらいの規模なのだろうか?こちらについては人口動態統計が利用できる.平成23年度の調査結果によると,「不慮の事故」による死亡者数は33,510人である.
4. 傷害ピラミッド
以上のデータに基づいて日本における傷害ピラミッドの図を書くと次のようになる.
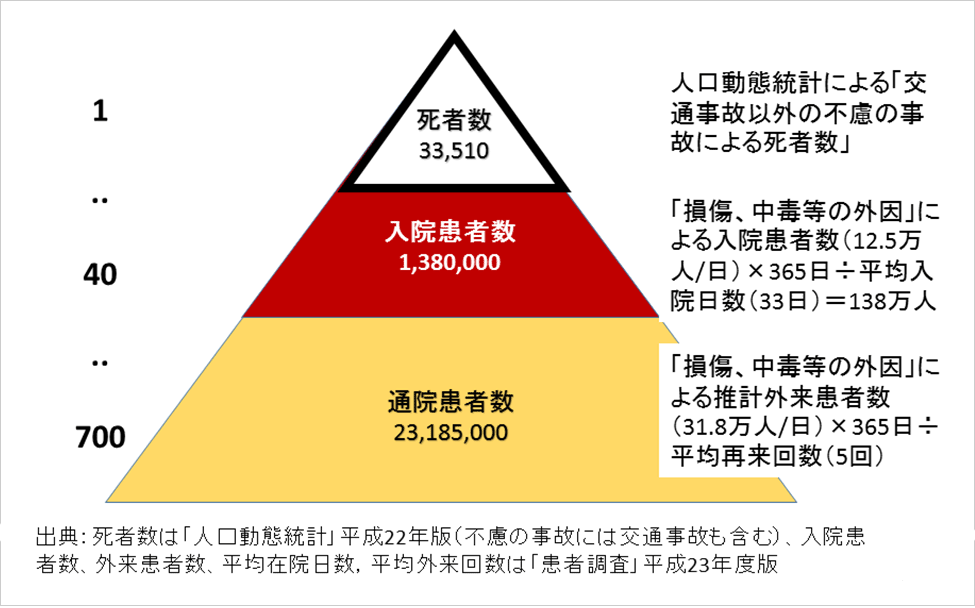
参考 EUの傷害ピラミッド