リスク情報コーディングマニュアル
1. 本マニュアルの目的
長岡技術科学大学安全安心社会研究センターは産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター(現在は人工知能研究センター)と共同して,科学技術振興機構の社会技術研究センター(JST/RISTEX)の平成26年度採択研究課題として「生活空間の高度リスクマネジメントのためのエビデンス情報基盤」と題する研究開発に取り組んでいる.これは既知の傷害情報と生活空間に関する様々なリスク情報を関連付けることにより,生活空間のリスクマネジメントに有用な様々なリスク情報を抽出するための情報基盤とその活用の方法論の開発を目指したものである.
本マニュアルは,このうち既知の傷害情報の記述に関する枠組みについて解説するとともに,既存の各種傷害情報データバンクに収録されている傷害情報データを統一的な基準のもとで再構成するためのコーディングの基準を与えることを目的としている.
平成27年3月に第一次稿を発行したが,その後,様々な拡張,改良を加えたものがこの第二次稿である.今後,研究開発の進展に伴って随時,拡張,改訂していく予定である.
なお,本マニュアルを用いたさまざまな活用事例の詳しい解説については,本マニュアルの最終版に掲載する予定である.
2. 傷害情報記述枠組みの考え方
WHOの定義によると,傷害の発生は身体が人間の耐える閾値を超えるエージェント(agent)に急激に曝露されたことによるもので,エージェントには,力学的エネルギー,熱,電気,化学物質,電離放射線などがある.傷害の発生には四つの要素があり,それぞれ,ホスト(host, 傷害を受けた人),エージェント(Agent,傷害発生の原因となる機械力,エネルギーや物質),ベクター(Vector, 例えば,力を加えたり,エネルギーを移し又は妨害したりする人或いは物),環境(Environment)と呼ばれる.WHOの疫学モデルは以上の4要素から構成されるが,事故対策の優先順位を決定するには傷害の程度など事故の結果が重要である.結果が致死事故であるか重大な傷害であるのか,軽いけがであるのかの相違は事故対策に相違をもたらす.そこで,本稿は,傷害情報データバンクの記述枠組みとして,WHOの提案する疫学モデルの4要素に「傷害結果」を加えた5要素からなる傷害情報記述枠組み(IIDF: Injury Information Description Framework)を提案する.記述枠組みを与えるためには,概念モデルの各要素についてその属性項目(attribute)を定め,各属性項目にその記述に用いる語彙セット(vocabulary set)を定義することが必要である.表1にそれぞれの内容を示す.
- 人/host
ホストとは被害者である.個人として特定するための情報は傷害情報システムとしては必要でない.むしろ特定可能な情報が存在すると傷害情報の提供可能範囲を限定してしまうことになる.しかし,原因究明,対策検討の必要性からは,年齢などの属性情報が必須である.ISO12100:2010「機械類の安全性-設計の一般原則-リスクアセスメント及びリスク低減」の5.3.2項「機械類の制限の決定」が「リスクアセスメントでは性別,年齢,利き手又は身体的能力の限界(例えば,視覚又は聴覚の減退,体型,体力など)によって特定される人の予見可能な機械類の全使用範囲(例えば工業用,非工業用及び家庭用など)を考慮しなければならない」と述べるように,ホストの性別,年齢,身体的能力の限界の存在に関する情報はリスクアセスメントにとっての必須項目である.
ISO/IECガイド50「安全側面-子供の安全の指針」によればリスクを評価する際に子供の認識力や運動力の発達に配慮しなければならない.特に生後1~2年の子供は認識力が未発達であり,運動力も日々変わっていくため,ホストが2歳以下の場合,月齢まで記録することが望ましい.
また,ある種類の傷害は特定地域に集中することがあるので,地域も基本的な項目にすべきであり,各人種の文化において,ものに対する認識なども差異があるため,人種や地域・国名も必要な項目と考えている. - 物/vector
物とは傷害原因物のことで,製品だけではなく,人や動植物なども含めている.本稿では,物を記述するあたり,「起因物」(傷害をもたらすもととまったもの),「関連物」,(事故に関連があるが,主因でないもの),「加害物」(傷害をもたらした直接のも)は必須項目である.
「起因物」と「加害物」は同一になる場合もあり,異なる場合もある.起因物の出自,状態なども傷害原因の究明や責任の追及などに重要な情報となるため,傷害情報システムにとって不可欠な事項である.製品の「型式・機種」,製造・輸入・販売業者などの「業者名」,及びリスクアセスメントに参考になる「(事故時までの)使用期間」も追加してよいと考えられる. - エージェント/agent
エージェントはある結果を引き起こす機械力やエネルギーであり,また,人が負傷するメカニズムに関係する要素ともいえる.本稿では,エージェントに関する情報を「危険源」(機械的危険源,熱的危険源など),「メカニズム」(転倒・転落,物体との衝突または打撲など),「傷害原因」(設計問題,経年劣化,誤使用など),「火災の有無」などの4項目によって記述することを提案する.火災の影響は広域にわたるため,特別に扱う必要があると考えた.
なお,事故発生のメカニズムについては,傷害状況が複雑だったり,新種類の事故などの場合,標準的な記述語彙リストでは不十分な場合も予想される.こうした場合,ある程度自由記述方式も取り入れて補完する必要があろう.このためには自由記述欄である「事故概要」の項目を備考欄に追加する.
本記述枠組みではWHOの開発した国際分類群(WHO-FIC: WHO Family of International Classifications)から国際疾病分類(ICD: International Classification of Diseases and Related Health Problems)及び国際傷害外因分類(ICECI: International Classification of External Causes of Injury)の二つの分類を参照している.前者ICDは日本でも人口動態統計をはじめ医療関係統計では広く採用されているものである.一方,後者のICECIについては世界的にもまだ広く使われているとは言えないが,その名が示す通り傷害情報の分類のために特別に開発された分類であり,既に米国のCDCが使いやすいショートリストを開発しているなど,今後世界的に利用が広がると予想されることから採用した.まだ和訳が公表されていないことから我々独自に翻訳を試みた.
なお,ICD及びICECIでは分類が示されているだけで,完全なコード体系として示されていないケースも多い.このため,本マニュアルに示すコードは本マニュアルの執筆者が独自に付番したものであることに注意されたい. - 環境/environment
傷害環境は,傷害が発生した時間,場所,傷害時における被害者の行動類型等で構成される.交通事故,労働災害といった分類法は,傷害を受けた場所,あるいは傷害を受けた時点での被害者の行動類型に応じて傷害を捉えたものであり,いわば,傷害情報のうち,環境に関する情報を利用して傷害を分類しているといってよい.医療事故,学校事故などといった捉え方と同様である.
本稿では,傷害環境に関する情報を自然環境と人工環境の二つに分け,「発生日」,「発生時間」,「天候状況」,「自然災害」(以上は自然環境),「活動分類」,「発生場所」,「起因物の利用頻度」,「起因物の置き場所」,「保護措置の実施」,「利用段階」,「当時製品の状態」,「居住環境」(以上8項目は人工環境)の12項目で構成する.前4者は日時,天候,自然災害といった自然的環境を,後8者は傷害発生時における被害者の活動内容や人工物環境としての場所,起因物とのかかわりを記述する環境情報を示す.保護者による見守りの状況といった社会環境も傷害の発生に関係があると考ている. - 傷害結果/consequence
ここで,傷害結果とは,事故に至る人の傷害のひどさおよび物の損害程度の二つの情報からなる.危害の程度は対策の優先順位の決定に極めて重要であり,リスクの大きさの評価にも不可欠な要素である.また,事故を防ぐため,調査の状況や対策の公表など採用した措置は社会のリスクマネジメントに貴重な資料となる.本研究では,結果に関する情報として,「危害の程度」(人の負傷程度&物の損害程度),「傷害部位」,「負傷の種類」(やけど,中毒,骨折など),「治療分類」(治療なし,追加治療,入院など),「被害者の人数」,「対策の実施」の6項目を基本的な記入内容と考える. - 備考情報/remark
事故情報の管理のために設けられた一連の情報,「ID番号」,「報告日」,「情報源」,「調査の状況」,「事故原因の判明」,「リコール公表日」と「事故詳細」(記述文章)の7つの情報を備考情報とする.
3. 傷害発生モデル及び傷害情報の属性項目
日常生活において発生する傷害には様々なものがあり,それぞれの傷害をもたらした原因は多数の要素が複雑にからみ合うため,その実態を系統系に記述するためには工夫がいる.前項で述べたように本マニュアルはWHOの疫学モデルをベースとした五要素に基づく記述枠組みを基礎としているが,疫学モデルの場合,傷害発生の一つの原因となる被害者の不安全行動について明確に捉えることができない.この問題を解決するために,第二次稿では,〓〓が作成した「労働災害分類の手引き」(昭和〓年)を参照して,特に危険源としてのヒトの行動等を的確に記述するための拡張を行った.「労働災害分類の手引き」は被害者であるヒトの「不安全な行動」と原因物であるモノの「不安全な状態」の両方の要因を記述している.そこで,五要素の一つであるホストについても,それが危険源となりうる側面を的確に記述するため,属性項目を補充した.このため,エージェントの中には危険源と並んで,「人の動作」という属性項目も含まれる.(図1参照)
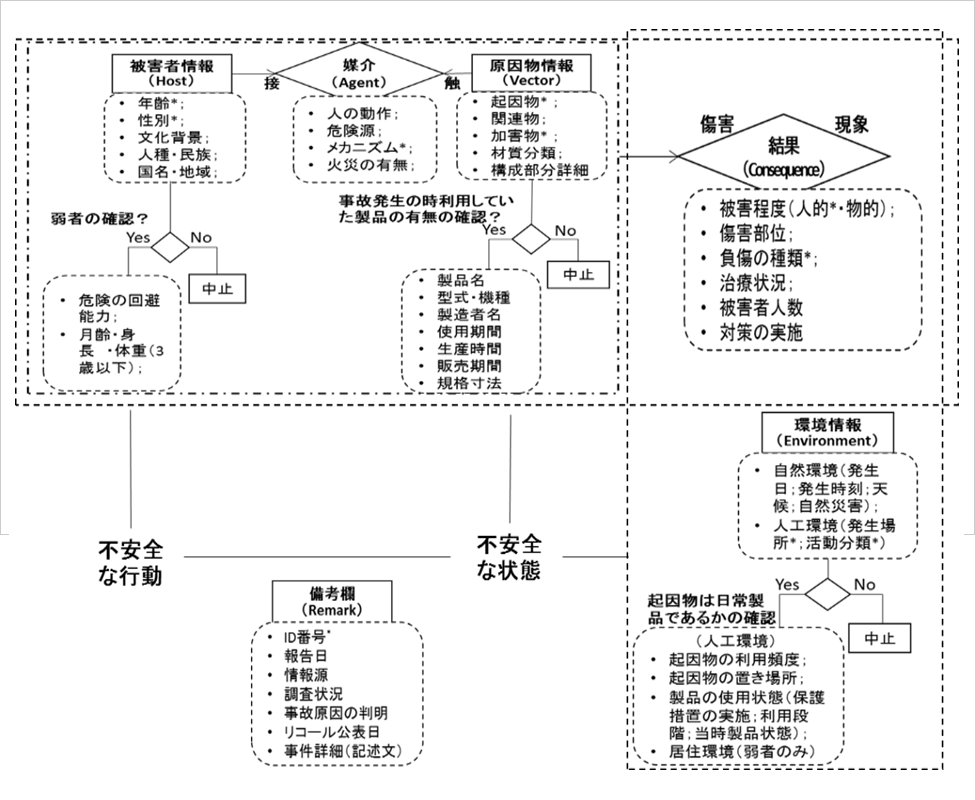
図1 傷害発生モデルと傷害情報の各属性項目
注:*付けている属性項目はWHOなど国際統計標準による必須項目であり,その以外の項目は選択可項目である.)
4. 起因物,関連物,加害物
第二次稿では起因物,関連物,加害物に関する記述方式についての大きな改定を行った.事故発生のプロセスには多数の要因が関与しており,そこには使用している製品や,周辺にあって事故発生の経過に影響を与えたもの,被害者に対して直接に危害を与えたものなど,あるいは事故発生の引き金を引いた人間の行動などがありうる.第二次稿では,WHOのICECIに準じて,これを起因物(initiating),関連物(intermediate),加害物(direct)という三区分を設けて,それぞれについてその属性を記述することを求める.
以下に,前項で示した図2の持つ意味をより具体的に示すために,NITEデータベースに記述されている「事故通知内容」「事故原因」の二つ項目の自由記述文章の内容を,本マニュアルの想定する枠組みに沿って再整理してみた.その結果を以下に示す.
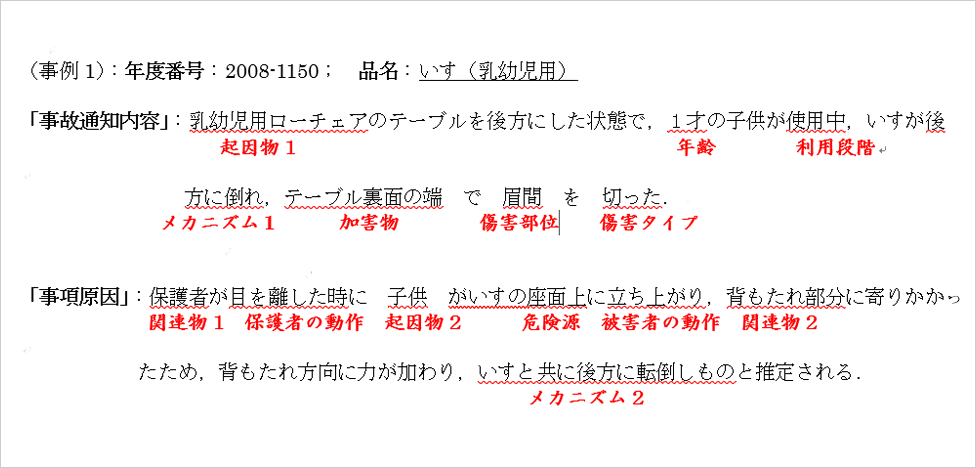
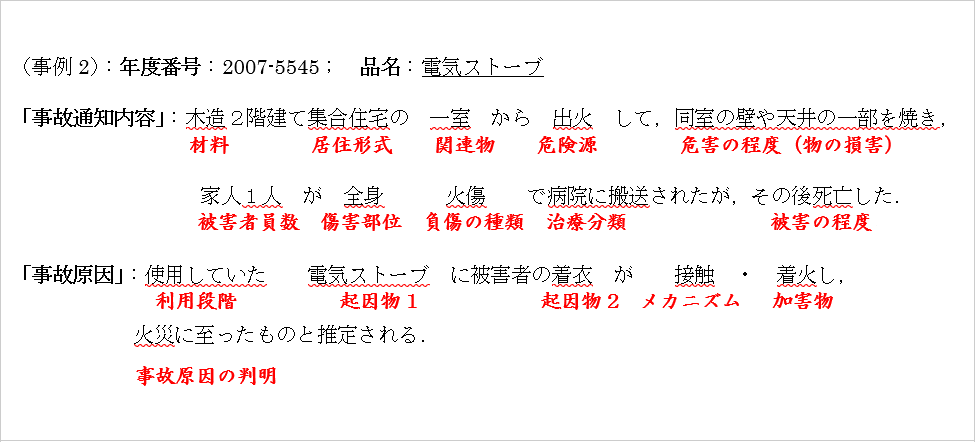
上記に示すように,ICECIに基づいて傷害情報のコード化を行う際には,“Mechanism” と“Object / Substance”の二つ属性項目のそれぞれについて,“Underlying (involved at the start of the injury event)→ Intermediate(involved in the injury event) → Direct(producing the actual physical harm)”という三段階に分けて情報の記入を求める.
この記述方法を別の角度から説明するために,ICECIの傷害プロセス三段階記入法(Underlying,Intermediate,Direct)及びNITEデータベースの被害の種類(被害なし,製品破損,傷害あり)という2次元マトリックスの形で,「もの」をキーとして,NITEデータベースから選んだ3件の乳母車事故を記述してみた.これを図3に示す.被害のなかったインシデント,人間への被害の生じていない製品破損事故まどで含めてデータベース化を行うことにより,なぜインシデントから事故へとプロセスが進行したのかを解明することに役立つだろう.これは,高度な製品安全マネジメント,リスク管理実現にとって重要なエビデンス情報を提供することになる.
図2 NITEデータを用いて,傷害情報整理の活用事例
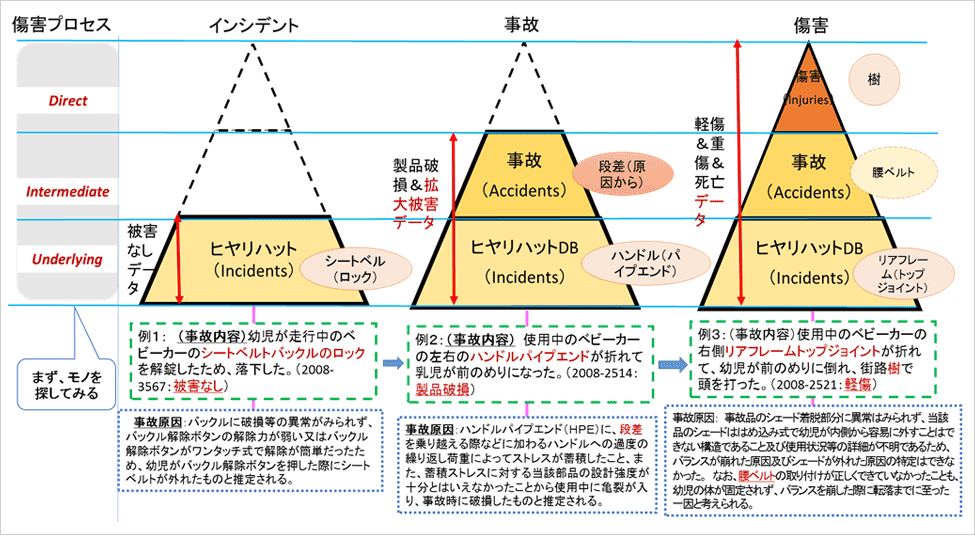
現存のさまざまな分野において日常傷害とかかわる情報データベースがあるが,それぞれのフォーマットも記述形式も統一されていないため,貴重な情報が大事に保存されているにもかかわらず十分に社会へ還元することができないでいる.本マニュアルにおいては,IIDFのフォーマットを用いて,現在日本国内に存在している各省庁保有の傷害情報の内容を表1に整理してみた.今後傷害情報の利活用技術開発の切口になると考えている.
表1 傷害情報記述枠組み(IIDF)に基づく生活空間リスク情報にかかわる国内各DBの収録項目の整理
| 要素 | 各国内DB (作成機関)属性項目 |
NITE ADB | NITE RDB | KDDB | 死亡届け・死亡診断書 | レセプト情報 | 救急搬送 | 火災調査* | 消費動向調査 | 国勢調査 | 学校事故事例検索DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NITE) | (NITE) | (産総研) | (市区町村・医療機関) | (厚生労働省) | (総務省消防庁・医療機関) | (総務省消防庁) | (内閣府) | (総務省統計局) | (日本スポーツ振興センター) | |||
| ホスト | 年齢 | ※ | × | ※ | ※ | ※ | ※ | ー | ※ | ※ | ※(学年) | |
| 月齢 | × | × | ※ | ※ | × | × | ー | × | ※ | × | ||
| 性別 | ※ | × | ※ | ※ | ※ | ※ | ー | ※ | ※ | ※ | ||
| 子どもの場合 | 発達段階 | × | × | ※ | × | × | × | ー | × | × | × | |
| 体重 | × | × | ※ | ※ | × | × | ー | × | × | × | ||
| 身長 | × | × | ※ | ※ | × | × | ー | × | × | × | ||
| 危険の回避能力 | × | ※ | × | × | ー | × | × | × | ||||
| 人種・民族 | × | × | × | × | × | × | ー | × | × | × | ||
| 国家・国籍 | × | × | ※ | × | ー | × | ※ | × | ||||
| 文化背景(学歴・職業) | × | × | × | ※ | × | ※ | ー | ※ | ※ | × | ||
| 消費者意識調査 | × | × | × | × | × | × | × | ※ | × | × | ||
| ベクター | 原因物 | Ⅰ起因物 | ※ | ※ | × | ※ | × | × | ||||
| Ⅱ関連物 | × | × | × | × | ||||||||
| Ⅲ加害物 | × | ※ | × | ※ | × | × | ||||||
| 主に利用されている製品にかかる情報* | 製品名 | ※ | ※ | × | × | × | × | ー | ※(耐久消費財) | × | ※ | |
| 型式・機種 | ※ | × | × | × | × | ー | × | × | × | |||
| 製造者名 | ※ | ※ | × | × | × | × | ー | × | × | × | ||
| 使用期間 | ※ | × | × | × | × | ー | ※ | × | × | |||
| 生産時間 | × | × | × | × | × | ー | × | × | × | |||
| 販売期間 | × | × | × | × | × | ー | × | × | × | |||
| 材質 | ※ | × | × | × | ー | × | × | × | ||||
| 保護措置の使用 | × | × | × | × | ー | × | × | × | ||||
| 係る構成成分 | × | × | × | ー | × | × | ||||||
| 規格寸法 | × | × | × | × | ー | × | × | × | ||||
| 製品の利用段階 | × | × | × | × | ー | × | × | |||||
| 製品の利用状態 | × | × | × | × | ー | × | × | |||||
| 物の利用頻度 | × | × | ※ | × | × | × | ー | × | × | × | ||
| エージェント | 危険源 | Ⅰに関連 | × | × | × | ー | × | × | ||||
| Ⅱに関連 | ー | × | × | ※ | × | × | ||||||
| Ⅲに関連 | ー | × | × | × | × | |||||||
| メカニズム | Ⅰに関連 | × | ー | × | × | × | × | |||||
| Ⅱに関連 | × | ー | × | × | × | × | ||||||
| Ⅲに関連 | × | ー | × | × | × | × | ||||||
| 人の動作 | 被害者 | ー | × | × | × | × | × | |||||
| 保護者* | ー | × | × | × | × | × | ||||||
| 火災の確認 | ー | × | × | ※ | × | × | × | |||||
| 環境 | 発生日 | ※ | × | ※ | ※△ | × | ※ | ※ | × | × | × | |
| 発生時刻 | × | ※ | ※△ | × | ※ | × | × | × | ||||
| 天候 | × | ー | × | × | × | × | ||||||
| 自然災害 | × | ー | × | × | × | × | ||||||
| 活動分類 | × | ー | × | × | × | ※ | ||||||
| 発生場所 | × | ※ | ※△ | × | ※ | ※ | × | × | ※ | |||
| 主に利用している物の置き場所 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 居住環境 | 世帯特性 | × | × | × | ※ | × | ※ | ※ | ※ | ※ | × | |
| 地域(日本) | ※ | ※ | × | ※ | × | ※ | ※ | × | ※ | × | ||
| 結果 | 危害程度 | 人的 | ※ | × | ※ | × | ※ | ※ | × | × | ※ | |
| 物的 | ※ | × | × | × | ※ | × | × | × | ||||
| 損害額 | × | × | × | × | ※(請求点数・金額) | × | ※ | × | × | × | ||
| 負傷の種類 | × | ※ | ※ | ※(傷病名) | ※ | ※ | × | × | ※ | |||
| 傷害部位 | × | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | × | × | ||||
| 治療状況 | × | ※ | ※ | ※(各関連詳細) | ※ | × | × | × | ||||
| 傷害のタイプ | × | × | ※ | ※ | × | ※ | × | × | × | |||
| 被害者人数 | × | × | × | × | ※ | × | × | |||||
| 事故原因の判明 | ※ | × | ※(死因) | × | × | × | × | × | ||||
| 対策措置 | ※ | × | × | × | ※ | × | × | × | × | |||
| 備考欄 | ID番号 | ※ | ※ | ※ | (氏名) | × | ※ | × | × | × | ※ | |
| 報告日 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※(診療開始日/実日数) | ※ | ※ | × | × | × | ||
| 情報源 | ※ | × | ※ | ※ | ※(医療機関) | ※ | ※ | × | × | × | ||
| 不具合部分 | × | × | × | × | ※ | × | × | × | ||||
| リコール公表日 | × | ※ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 調査状況 | × | × | × | × | × | ※ | × | × | × | |||
| 記述文章(詳細) | ※ | ※ | ※ | ※ | × | ※(治療詳細) | ※ | × | × | ※ | ||
| 画像(診断など) | × | ※ | ※ | × | ※ | ※ | × | × | × | × | ||
(注:※標準項目あり;:標準項目ごとにわけられてないが、叙述の中に含まれる場合がある; ×:項目なし。)2.略称について: NITE ADB:製品評価技術基盤機構 事故情報データベース;NITE RDB:製品評価技術基盤機構事故 社告・ リコールデータベース;KDDB:産業技術総合研究所キッズデザインデータベース; ー:具体的な内容を確認できず;※△:外因による死亡の場合、傷害したまたは死亡時点での関連情報を求める。 *利用されている製品:危険事件が発生した際、主に利用されている製品に関わる情報であり、なお、当時に利用されている製品は起因物にも、関連物にも、加害物にもなる可能性があると考えている。*保護者: 子どもや介護がいる人などの場合、危険事件の発生際に、それらの行動詳細について求められる場合がある。*:火災調査の 場合、人と物に関する詳細情報は事後調査、原因判明後による報告する場合が多く;)
5. 標準語彙リストの情報源
標準化され,かつコード化された情報を利用することによって傷害情報を最大限に利用することが可能となる.このため,本マニュアルにおいては,図2に挙げた各属性項目について,できる限りWHOやISOの国際標準と各国の国内標準で規定されている語彙リストを用いる.しかし,傷害の解明と製品設計の改善などに必要と考えている幾つかの属性項目にについては現時点で参照できる国際標準等が存在していないため独自の分類コードの開発も行った.
表2 IIDFが採用した標語語彙リストの情報源
| レベル | 標準名 |
|---|---|
| 国際 |
|
| 国内地域 |
|
| 組織 |
|
| 独自 |
|
6. 本マニュアルの色
上記の工夫により,本マニュアルに基づく傷害データは以下のような特色を発揮する.
- 国際的比較が可能;
- データマイニングの作業時間が削減;
- 客観的な定量リスクアセスメントが可能;
- 各データの統合管理によるコストの削減;
- 論理性がある階層的なデータ表現を持ち,すべての利用者にとって便利;
- 官民共用情報交換の土台になる;
7. 本マニュアルの執筆者
本マニュアルは,長岡技術科学大学及び産業技術総合研究所に所属する研究グループのメンバーがこれまで取り組んできた様々な研究の成果を取り入れて作成したものであるが,執筆に当たっては,産業技術総合研究所人工知能研究センターの一員であり,長岡技術科学大学安全安心社会研究センターの特別研究員でもある張坤(JSPS外国人特別研究員)と研究代表三上喜貴が中心となって取りまとめを行った.独自開発された語彙リストの作成者は飯澤祐貴,佐藤順子,横田佑香里の三人で行い,印刷原稿の整理は飯澤祐貴君が行った.
また,付録に添付した統合危険源リストは,科研費研究課題「市場監視の時代における傷害情報サーベイランス」(平成25年度~平成27年度,研究代表者は三上)の研究の一環として長岡技術科学大学システム安全系福田隆文教授及び飯沢祐貴君が開発した成果である.
